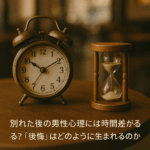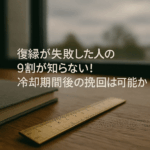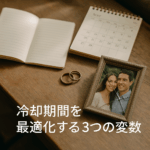復縁できない理由は愛情の量ではなく“相手の記憶に残る質”にある
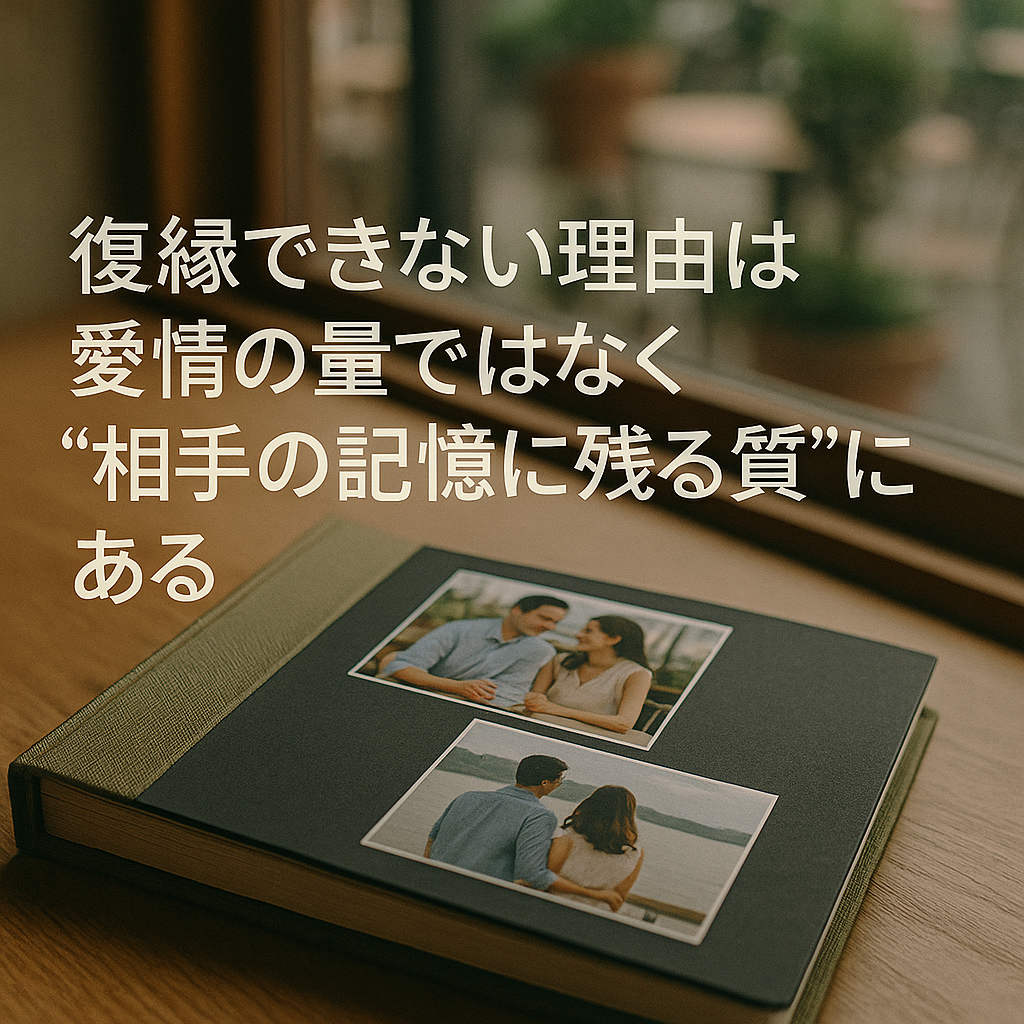
なぜ復縁できない人ほど「まだこんなに好きなのに」と嘆くのか。その理由は、愛情の量が復縁を決めるのではなく、別れの記憶にどのように残っているかという“質”こそがカギだからである。人は、感情的に負担が大きい関係からは距離を置こうとする傾向があり、どれだけ好意があっても、「疲れた」「面倒だ」と記憶されていれば、再接近は心理的に困難となる。本記事では、復縁が失敗する本質的な理由をら読み解いていく。
なぜ「復縁できない理由」は愛情不足では説明できないのか
復縁を望む女性の多くが、「私はあれほど彼を愛していたのに、なぜ復縁できないのか」と悩む。しかし実際、愛情をたくさん注いだことと、復縁が叶うことの間に明確な相関はない。愛の“量”ではなく、“どのように記憶されていたか”が復縁の可否を左右する要因である。この節では、「なぜ愛情の多さでは説明できないのか?」という疑問に、記憶心理学・感情心理学の視点から答える。
復縁が成立するかどうかは、別れた相手の記憶に自分という存在がどのように残っているかに大きく依存している。たとえ多くの愛情を注いでいたとしても、それが相手の中で「負担だった」「しんどかった」として記憶されていれば、復縁の可能性は極端に低くなる。逆に、少ない愛情表現でも「一緒にいて楽だった」「自然体でいられた」と記憶されていれば、再接近の心理的障壁は低い。
心理学では、感情的記憶は中立的記憶よりも再生されやすく、印象形成に強く影響することが知られている(Conway&Pleydell-Pearce,2000)。
特に別れの際に強いネガティブ感情と結びついた記憶は、「あの人=疲れた」「責められた」といった情動的ラベリングを伴って保持される(Kensinger, 2004)。
また、復縁が成立したカップルの多くが、「当時はうまくいかなかったけど、今思えば居心地がよかった」と語る傾向があるという調査結果もあり(佐々木, 2019)、“記憶の中の印象”がポジティブに変化していることが再接近の動機となっていることが示唆されている。
このように、復縁の可否は“どれだけ愛されたか”ではなく、“どんなふうに記憶されているか”に大きく依存している。愛情表現が過剰だったり一方的だったりすると、「圧」「義務感」「自己喪失感」として記憶され、ネガティブな感情と結びついてしまう。
したがって、「なぜ復縁できないのか」という問いに対しては、「記憶に残る質を見直す必要がある」という視点が不可欠である。これを理解せずに「もっと愛したい」と感情量で押してしまうと、かえって相手の心理的距離を広げる結果になりかねない。
感情の総量よりも「記憶に残る質」が復縁を左右する理由とは
恋愛において「どれだけ相手を愛したか」を誇りに思う人は多い。しかし、復縁において重要なのは、相手の中にその“愛された記憶”がどう残っているかである。つまり、感情の総量よりも、その感情が相手にどのような印象として蓄積されているか=“記憶の質”が結果を左右する。
多くの人が陥る誤解は、「強い愛情を注げば、その分だけ相手の心に残る」という直線的な思考である。だが実際は、“どのように感じさせたか”“どんな印象を残したか”こそが記憶に深く刻まれる。
たとえば、同じように「好き」と言っても、「安心できた」「プレッシャーだった」という印象は全く異なる。つまり、復縁の鍵は“記憶に残る情動の質”をどう設計できたかにかかっている。
記憶心理学においては、情動を伴うエピソード記憶が長期記憶として強化されやすいことが知られている(McGaugh,2003)。特に恋愛記憶のような自己関連的エピソードは、「印象の強さ」と「感情の質」によって再生の可能性が大きく左右される。
また、Neisser(1982)は、「フラッシュバルブ記憶」として知られる、感情的に鮮明な記憶の存在を指摘しており、強く愛されたとしても、その情動が“心地よさ”ではなく“苦しさ”と結びついていれば、記憶はむしろ負のトリガーになり得る。
このように、感情の量より“相手の主観的記憶にどう残っているか”が復縁に直結する。感情の質が高く、「安心」「楽しい」「認められた」という印象として残っていれば、再接近の際にそれがポジティブな動機として機能する。
一方、「責められた」「振り回された」などのネガティブ印象が残っていれば、どれほど多くの愛情があったとしても、それは“負担として記憶されている”可能性がある。
復縁の成否は「どれだけ愛したか」ではなく、「どんな感情を残したか」で決まる。記憶は感情によって形づくられ、関係の未来を静かに左右している。
愛された記憶が残っていないと復縁できないのはなぜか
「自分はあれほど彼を大切にしてきたのに、なぜ忘れられたのか」と感じる人は少なくない。しかし、復縁の可否は「どれだけ愛したか」ではなく、相手の中に“愛されたという記憶”が存在しているかどうかによって大きく左右される。
では、なぜ「愛された記憶」が残っていないと、復縁は成立しないのか?
愛された経験が記憶されていない、あるいはその記憶が薄れている場合、相手は「関係を再び持つ意味」を感じにくくなる。復縁とは、感情の再接続であると同時に、過去の関係に対する“再評価”のプロセスでもある。その際、ポジティブな記憶がなければ、再評価に値するものがなくなり、再接近の動機が生まれにくい。
日常記憶研究においては、「感情的な出来事ほど記憶に強く残る」という知見がある(Kensinger,2004)。しかしこれは、愛された事実があっても、その記憶が相手にとってポジティブに意味づけされていなければ残らないことを意味する。
また、Conway&Pleydell-Pearce(2000)の自己記憶システム理論では、人は現在の自己像と整合的な過去の記憶を優先的に保持・想起する傾向がある。つまり、「あの人に愛された」という記憶が、現在の自分にとって肯定的な意味を持たなければ、記憶の表層から後退してしまう。
このように、復縁の起点となるのは“愛されたという確信”が相手の中に存在しているかどうかである。どれほど尽くしていたとしても、その記憶が相手にとってプレッシャーや義務感と結びついていた場合、記憶されないか、むしろネガティブなラベルで保持される。
復縁とは、かつての“関係の意味”が記憶の中にどのように保存されているかによって決まる。だからこそ、愛情を注ぐことだけでなく、「相手が愛されたと実感できる体験を積ませていたか」を振り返る必要がある。
復縁できない人に共通する記憶に残りにくい特徴とは
復縁を願っても、相手から「記憶にすら残っていない」「なんとなく印象が薄い」と受け取られてしまえば、その可能性は著しく低くなる。
恋愛において大切なのは、好かれることよりも“記憶に残ること”である。では、復縁できない人たちにはどのような「記憶に残りにくい特徴」があるのか。
記憶に残らないということは、感情が揺れなかった、あるいは印象が薄かったということである。特に、「優しすぎる」「当たり障りがない」「自分を出さない」といった傾向は、恋愛初期では好印象でも、長期的には相手の記憶に残りづらい。そのため、別れた後に思い出される機会も少なく、復縁という再接近の可能性が著しく下がる。
印象形成に関する心理学的研究では、「ユニークさ」「意外性」「感情の揺さぶり」が記憶の定着を促す要因であることが知られている(Asch,1946)。また、Kahneman(2011)の「ピーク・エンドの法則」では、人は出来事全体よりも、最も感情が動いた瞬間(ピーク)と最後の印象(エンド)を記憶する傾向がある。
つまり、感情的なやり取りや印象的な体験がなかった関係は、たとえ長く続いていたとしても記憶に定着しにくい。この点で、「波風を立てないこと」が恋愛維持には有利でも、復縁という文脈では不利に働く可能性がある。
このように、記憶に残りにくい人の特徴は、“悪くないけど特別でもない”という曖昧なポジションにあることに起因する。恋愛においては、安心感だけでなく、「その人にしかない個性」や「感情の揺れ動き」が相手の記憶に残るフックとなる。
復縁とは“思い出されること”から始まる。そのためには、記憶に残る言葉・体験・関係性を築けていたかが鍵になる。優しさだけでは足りず、「感情を動かしたかどうか」が記憶にアクセスできるかどうかを決定づける。
いい人で終わる人はなぜ印象に残らないのか
「優しかったのに」「ちゃんと尽くしたのに」と思いながらも、なぜか復縁の対象に選ばれない。その背景には、「いい人」としては評価されても、“印象に残る相手”としては認識されていないというギャップがある。
本節では、「いい人」で終わる人が記憶に残りにくい理由を、印象形成と記憶心理の視点から明らかにする。
「いい人」は一般的に“無難”で“安心感がある”とされるが、その反面、個性や感情的インパクトに欠けることが多い。恋愛の記憶は、単なる“好印象”よりも、“感情の揺れ”や“独自性”と強く結びついて形成されるため、波風の立たない関係は記憶に残りにくい。
つまり、いい人すぎることで、恋愛相手としての「物語性」や「象徴性」を欠き、“過去の誰か”として埋もれてしまうのだ。
印象形成研究において、Asch(1946)は、人の印象は「中心特性」によって大きく形成されると述べている。つまり、「優しい」「真面目」といった特性は評価されやすい一方で、記憶に残るような“際立ち”にはなりにくい。
また、Fiske&Taylor(2013)は、社会的記憶の保持には「注意を引いた要素」や「期待とのズレ」が重要であると述べており、「良いけど特徴がない」存在は、情報処理上も記憶に残りづらい。
このように、「いい人」とは相手にとって“安心できるが、思い出す必要のない存在”になってしまいやすいというパラドックスを抱えている。恋愛においては、印象に残る出来事や、その人らしい発言・反応が、記憶のなかで感情と結びつき、後の再評価や復縁のきっかけとなる。
復縁を望むなら、“好かれていたか”ではなく、“思い出される存在だったか”を問うことが重要である。「いい人」から一歩踏み出し、感情を共有し、自分らしい軌跡を残すことが、記憶の中に確かな“存在感”を築く第一歩となる。
自分語りばかりする人が関係を築けない心理的要因とは
恋愛の場面で、自分のことを一生懸命伝えようとする人は少なくない。しかし、会話の中心が常に自分になってしまうと、相手との心理的距離は縮まるどころか、「一緒にいて疲れる」「話が通じない」といった印象を残す。
特に復縁の文脈においては、過去のコミュニケーションスタイルがどう記憶されていたかが鍵となるため、「自分語りばかりしていた人」は不利な立場になりやすい。
自分語りが多い人は、自分の存在価値を示そうとしているつもりでも、相手にとっては「一方的で共感されない存在」として認識されやすい。恋愛関係の維持や記憶形成においては、相互作用と感情の共鳴が不可欠である。
自分ばかりが話すことで、相手の内面にアクセスする機会を奪い、「関係性」ではなく「自己アピールの場」として記憶されてしまう。
会話分析の研究では、人は自分が「理解されている」と感じたときに、相手との関係を肯定的に評価することがわかっている(Reis&Shaver,1988)。また、Baumeister&Leary(1995)は、人間には「他者と意味のある関係を築きたい」という基本的欲求があると指摘しており、一方通行の会話はこの欲求を満たさない。
さらに、復縁に至ったカップルの会話を分析した研究(坂本,2020)でも、復縁成功者の多くが「相手の話をよく聞く」「以前の関心を覚えている」など、共感的態度を重視していたことが示されている。これは、自分語りよりも「相手への感受性」が記憶に残りやすいことを示唆している。
このように、自分語りばかりする人は、結果として“対話の中に相手の存在が含まれない”記憶を残しやすい。たとえ好意や興味があったとしても、相手が「自分は大切にされていなかった」と感じていれば、その印象は記憶に深く残り、復縁の可能性を下げる。
恋愛において大切なのは、語ることではなく、“共にいる感覚”を残すことである。自己開示と共感は対になってこそ意味を持つ。記憶に残る関係とは、「話したこと」よりも「心を通わせた実感」があったかどうかで決まるのだ。
復縁できない人が無意識に繰り返している「やってはいけないこと」とは
「なぜ復縁できないのか」と悩む人の多くが、実はその原因に気づいていない。無意識のうちに“やってはいけない行動”を繰り返してしまっている場合があるのだ。
その行動は、相手の気持ちを取り戻すどころか、逆に心理的距離を広げてしまう原因となっている。ここでは、復縁を阻む“見えにくい失敗行動”に焦点を当てる。
復縁を望むあまり、多くの人は「自分の気持ちを伝えたい」「謝りたい」「誤解を解きたい」と思い、感情的に連絡を取ったり、頻繁に相手を気にかける行動に出たりする。
しかし、別れた直後の相手は感情の整理途中であることが多く、過剰な接触は“プレッシャー”や“執着”として受け取られる危険性が高い。特に、「返信がないのに何度もLINEする」「SNSを監視する」「共通の友人を通じて探りを入れる」といった行動は、信頼の回復ではなく、相手の警戒心を強めてしまう。
行動経済学の「心理的リアクタンス理論(Brehm,1966)」によれば、人は自由を制限されると、それに対抗しようとする傾向を示す。つまり、別れた後に相手の領域を侵すような行動を取ると、復縁どころか「自由を脅かす存在」として認識され、拒絶される可能性が高まる。
また、感情心理学の研究(Frijda,1986)では、相手が感情を処理する時間を必要とする段階で過干渉が入ると、感情の“圧縮”ではなく“拡散”が起きやすく、相手の不快感が増幅されるとされている。
このように、「自分では善意のつもりの行動」が、相手の視点からは“侵入”や“操作”として認識されることがある。
復縁において重要なのは、「自分の気持ち」ではなく「相手の心理状態とタイミング」を尊重することにある。やってはいけない行動とは、“相手のペースを奪う行為”そのものである。
復縁を成功させるには、沈黙や距離をとる勇気こそが、最も戦略的な選択肢である。無意識の“焦り”が相手との再接続を遠ざけていないか、自問することから始めるべきだ。
冷却期間に焦って連絡する人が失敗する心理メカニズムとは
「もう我慢できない」「一言だけ伝えたい」、そんな衝動に駆られて、冷却期間中に連絡してしまう人は多い。だがその行動は、復縁の可能性を下げる大きなリスクを孕んでいる。
なぜ人は冷却期間を守れず、かえって関係を悪化させてしまうのか。その背後には、“不安”と“接触欲求”による心理的メカニズムが潜んでいる。
冷却期間中に連絡したくなる衝動は、「確かめたい」「つながっていたい」という不安回避的動機から生まれる。しかし、相手にとってその連絡は、“安心”ではなく“圧”として機能することが多い。
特に、別れた相手が「自由になりたい」「距離を取りたい」と思っている場合、連絡はその願いを打ち消す侵入行為となり、信頼の再構築を困難にする。
Bowlby(1969)の愛着理論によれば、不安型愛着を持つ人は、相手の不在や沈黙を強い不安として捉え、過剰な接触欲求に駆られやすい。また、連絡によって安心を得ようとする行動は、一時的な不安解消にはなるものの、相手の感情処理のプロセスを妨げてしまう(Mikulincer&Shaver,2007)。
さらに、冷却期間中の接触は、相手の「別れた意味」を強化するリスクがあることも指摘されている。つまり、「やっぱりこの人は自分のペースを尊重できない」と認識され、別離の正当化が進む(Rollie&Duck,2006)。
このように、冷却期間に連絡する行動の本質は「自分の不安の解消」であり、「相手のため」ではないことが多い。復縁は、相手の心が変化し、再び関係を築こうとする“内的動機”が生まれてこそ成立する。
焦りからの接触は、その芽を摘むどころか、「もう戻れない」という確証を相手に与えることすらある。
沈黙は不安の証明ではなく、信頼の構築である。冷却期間とは、相手の心のスペースを回復させ、自分自身の感情を整理するための戦略的な静けさなのだ。
相手に疲れたと思わせる言動パターンとは何か
別れ際に「もう疲れた」と言われた経験がある人は少なくない。この言葉は、怒りよりも深刻で、関係の継続を諦めたサインといえる。では、人はどのような言動に対して“疲労”を感じ、恋愛関係を手放すのか。
復縁を考える上で、この「疲れた」という感覚の正体を知ることは極めて重要である。
人が恋愛関係で「疲れた」と感じる背景には、一貫して心理的リソースが消耗される状態がある。具体的には、以下のようなパターンが挙げられる。
- 感情の起伏が激しく、常に対応を求められる
- 相手への依存や執着が強く、安心感を奪う
- 何度も同じ話を蒸し返し、解決に至らない
- 自己否定や不安を繰り返し吐露し、相手が「支える役」に固定される
これらは、相手にとって「関係を維持するコスト」が高くなる行動であり、恋愛関係そのものを“義務”として感じさせてしまう。
感情労働の概念を応用すると、他者の感情に過度に応答させられる状態は、心理的疲労を引き起こす(Hochschild,1983)。また、恋愛関係において「共感疲労」が起こると、相手との距離を取ろうとする行動が出やすくなる(Figley,1995)。
加えて、Carstensenら(2000)の社会情動選択理論では、人はストレスや否定的感情の多い関係から心理的に離れようとする傾向があり、「疲れた」という言葉は、感情的な“撤退信号”とみなすべきである。
このように、「疲れた」と思わせる言動は、感情の過負荷を相手に強いている状態であり、復縁において最も避けるべき記憶の一つである。
復縁とは、かつての記憶を肯定的に再構成するプロセスでもあるが、「一緒にいると疲れる」という印象が強く残っている場合、その記憶が再構成される余地は限りなく小さい。
大切なのは、“支えられる側”から“支え合える関係”へと転換できる自分を作ることである。復縁を目指すなら、自らの言動が相手の心理的負担になっていなかったかを冷静に省みることが、再出発への第一歩となる。
「もう無理かも…」と感じた時こそ復縁の本当のスタートである
復縁を望む人が最も心折れやすい瞬間は、「もうダメかもしれない」と感じた時である。しかし、その感情は決して“終わり”ではなく、むしろ自己変容と感情調整の始点となり得る。一度、相手への執着や期待を手放すことで、本質的な変化と関係の再定義が可能になるのだ。
「もう無理」と感じたとき、人は初めて“相手ではなく自分”に焦点を当て直すことができる。このプロセスは、単なる諦めではなく、自己主体性の回復である。
復縁を可能にするのは、「取り戻す」ための努力ではなく、“過去の関係性”とは異なる自分自身を再構築し、相手にとって新たな価値を感じさせられる存在へと変容することである。
行動変容における「トランスセオレティカルモデル」(Prochaska&DiClemente,1983)では、「無力感を感じる段階」は、自己認識を促進し行動変容へと移行する重要な契機であるとされている。
また、Emmons(1992)は、喪失や挫折体験をきっかけにした自己内省が、個人の価値観やアイデンティティの再構成を促すことを示しており、復縁においてもこのプロセスが有効に機能する可能性がある。
このように、「無理かも」と思った瞬間は、感情的執着から解き放たれ、より冷静に現実と向き合える心理的転換点である。このタイミングでの自己変容が、“過去とは違う自分”として相手の記憶に再び刻まれる契機になる。
復縁とは、かつての自分に戻ることではなく、相手の記憶に“新しい意味”で再登場することである。諦めの先にこそ、自分の軸を取り戻し、相手との再接続の土壌をつくる力がある。
諦めるべきかの問いは、復縁の質を変える内省の起点である
「もう諦めるべきだろうか」という問いは、復縁を望む人にとって最も苦しく、避けたい感情のひとつである。しかしこの問いは、感情の終点ではなく、自己との対話を深める出発点になり得る。
安易な希望にすがるのではなく、自分の内側を掘り下げることこそが、結果として復縁の“質”を高める鍵となる。
「諦めるべきか」という問いが立ち上がった時、人は初めて、相手軸から自分軸への転換を試みることができる。この内省のプロセスは、「なぜ復縁したいのか」「その思いにどんな自己イメージや価値観があるのか」といった、深層的な動機の再評価を促す。
このような内省によって、復縁が“相手を取り戻すこと”ではなく、“自分が変容すること”で実現する関係再構築であるという理解に到達する。
ここから、本当の意味で成熟したアプローチが可能になる。
行動科学におけるメタ認知研究(Flavell,1979)は、自分自身の思考や感情に対する気づきが、行動選択の質を高めることを示している。
また、カウンセリング心理学の視点からは、「自己の語り直し)」が自己理解を深め、感情調整を可能にする(White & Epston, 1990)。
さらに、坂口(2021)の質的研究によれば、復縁に成功した事例の多くは、「一度諦めたあとに自分と向き合った時間があった」と報告されており、このプロセスが心理的距離の再調整に不可欠であるとされている。
「諦めたくない」気持ちは自然だが、「諦めるかもしれない」と自問できる状態は、依存から主体性への転換点である。
この問いを回避せずに正面から受け止めることで、感情は整理され、より理性的かつ戦略的な復縁行動へと進化する。
復縁は、未練を手放すことからはじまる。諦めるかどうかではなく、「諦めようとしたとき、私は何に気づいたか」を問う姿勢こそが、過去を超えた新しい関係性への扉を開く。
復縁に疲れたと感じる時期が意味する心理的転換点とは
「もう疲れた…」、復縁を目指して努力を重ねてきた人が、ふとそう感じる瞬間がある。この疲労感は、単なる挫折ではなく、心が無意識に限界を知らせているサインでもある。
しかしその一方で、“疲れ”の感覚は自己変容への入口でもあり、感情の再構築が始まる重要な転換点となる。
「復縁に疲れた」と感じる状態は、心理的には“報われない努力”への内的フィードバックである。
この時期、人は無意識に以下のような問いを抱き始める。
- 自分ばかりが頑張っていないか
- この関係は本当に幸せにつながるのか
- 相手ではなく、何か別のものを埋めようとしていないか
このような問いは、単なる諦めではなく、依存的な執着から距離を取り、成熟した愛の形を再考する機会となる。疲労は“やめどき”ではなく、“考えなおす時期”なのだ。
Burnout理論(Maslach&Jackson,1981)によると、情動的労働の蓄積は“疲労”という形で現れ、回復にはリフレーミング(認知の枠組みの転換)が不可欠とされる。
また、感情調整に関する研究(Gross,1998)では、疲れを感じたタイミングでの再評価が、その後の行動選択や人間関係の質を高める効果をもたらすとされている。
さらに、日本の研究でも、長期的な片思いや復縁活動に取り組む人の中には、「一度“疲れた”と感じた後に、相手に対する捉え方が変わった」という語りが見られる(田中,2019)。
これは、疲労の感覚が感情の再統合を促進するきっかけになっていることを示している。
「疲れた」と感じることは、決して弱さや失敗ではない。むしろそれは、自分の感情に誠実に向き合い、限界と可能性の境界を自ら認識しようとする“成熟の兆し”である。
この転換点で大切なのは、無理に進み続けることではなく、一度立ち止まり、「なぜ疲れてしまったのか」を丁寧に振り返ることである。
復縁への最短ルートは、“疲れ”を無視して突き進むことではなく、“疲れ”を手がかりに本質を見直すことにある。
この再評価が、自分自身を回復させ、より健全な関係を築く準備となるのだ。
参考文献
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.
Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M., & Charles, S. T. (2000). Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. American Psychologist, 55(3), 165–181. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.3.165
Emmons, R. A. (1992). Abstract versus concrete goals: Personal striving level, physical illness, and psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 62(2), 292–300. https://doi.org/10.1037/0022-3514.62.2.292
Figley, C. R. (1995). Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized. Brunner/Mazel.
Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906
Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge University Press.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271
Hochschild, A. R. (1983). The managed heart: Commercialization of human feeling. University of California Press.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2(2), 99–113. https://doi.org/10.1002/job.4030020205
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. Guilford Press.
Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51(3), 390–395. https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390
Rollie, S. S., & Duck, S. (2006). Divorce and dissolution of romantic relationships: Stage models and their limitations. In M. A. Fine & J. H. Harvey (Eds.), Handbook of divorce and relationship dissolution (pp. 223–240). Routledge.
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. Norton & Company.
田中美佳(2019).「失恋経験における語りの構造と心理的回復プロセス」.心理臨床の広場,7(2), 45–54.
坂口明子(2021).「復縁経験者の語りにみる関係再構築プロセスの質的検討」.日本カウンセリング学会第53回大会発表論文集,203–206.